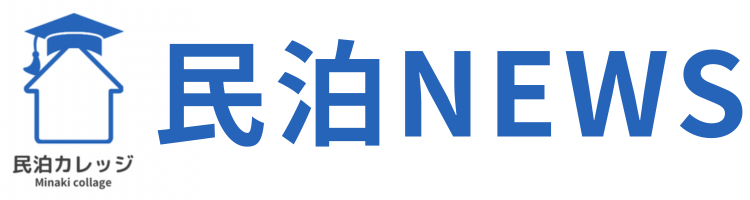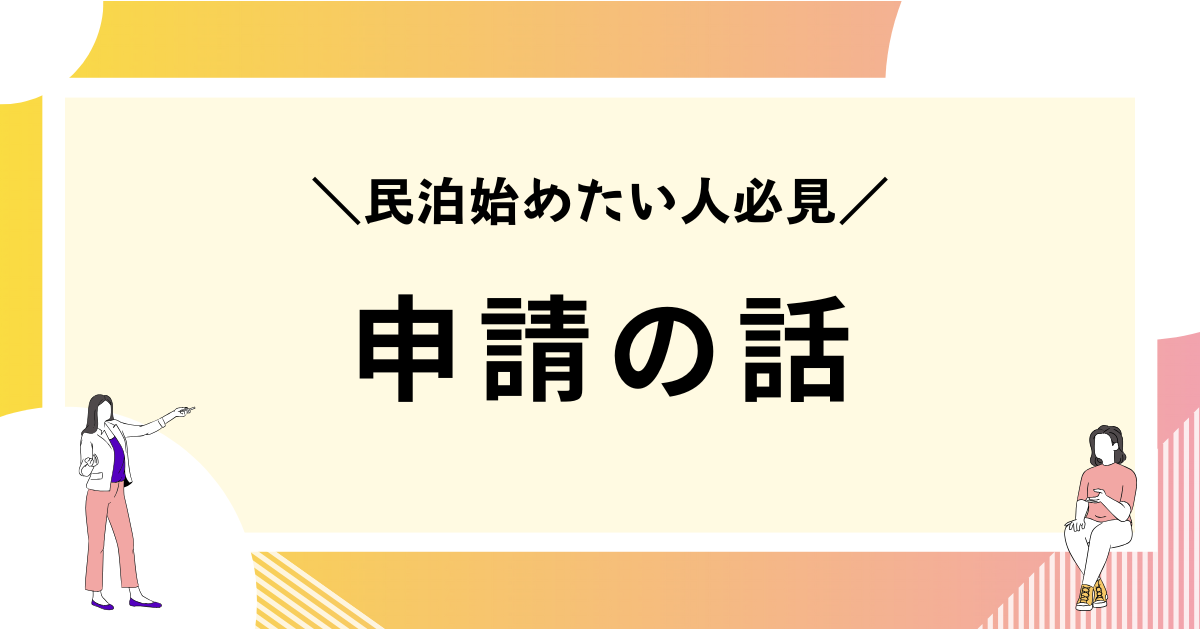こんにちは!今回は「民泊の始め方」について、お話していきます。法律や許可の話って、どうしても固くなりがちですよね。でも、やり方さえわかれば意外とスムーズに始められるのが民泊の魅力です。ぜひ気楽な気持ちで読み進めてみてください。
「民泊を始めたい」と思ったら、真っ先にぶつかるのは“どの法律でやるか”という壁。
さらに、都内や地方などエリアによってルールが違ったり、物件ごとに用意しなければいけない書類もまちまち。最初は「何をどうすればいいの?」と混乱してしまう方が多いです。
実は、調べるよりも先に、既に始めている人に聞く方が早いし確実です。自分であれこれ情報を探すより、知見を持った人との交流を通じて「ここはこうやるといい」「この段階でこういう届出が必要」といったリアルなアドバイスをもらうと、かなりスムーズに進みます。
本記事では、民泊に関する3つの代表的な法律・制度(住宅宿泊事業法、旅館業法、特区民泊)をざっくり解説しつつ、許可申請や書類準備の基本的な流れを紹介します。
さらに、都市部と地方での違いや、実際に弊社が物件を立ち上げるときに感じた苦労話も交えながらお伝えします。最後には、今後開設予定のコミュニティへの話や、講座・管理相談の情報も載せていますので、よかったら参考にしてください。
民泊には主に3つの制度がある
民泊と一口に言っても、実は大きく3種類の制度(法律)が存在します。どれを使うかによって申請先やルールが違ってくるので、まずはここを押さえておきましょう。
住宅宿泊事業法(民泊新法)
住宅宿泊事業法(民泊新法)には次のような特徴があります。
旅館業法(簡易宿所)
旅館業法(簡易宿所)には次のような特徴があります。
特区民泊(国家戦略特区)
特区民泊(国家戦略特区)には次のような特徴があります。
必要な許可・届け出と主な書類
次に「具体的にどこに申請・届け出を出すのか」と、「何が必要なのか」をざっくり整理します。
| 制度 | 申請・届け出先 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 都道府県知事(市区町村)への届出 | 年間180日以内。不在型は管理業者委託が必要。オンライン届出可 |
| 旅館業法(簡易宿所) | 保健所(自治体) | 営業許可が必要。書類や設備基準のハードルあり。営業日数制限なし |
| 特区民泊(国家戦略特区) | 特区に指定された自治体の担当部署 | 2泊3日以上など独自ルール。エリア限定。認定申請は比較的スムーズ |
主な提出書類の例
- 物件の登記事項証明書(賃貸ならオーナーの承諾書も)
- 間取り図、周辺地図、建物設備の概要
- 消防法令適合通知書(消防署に確認し、現地調査を受ける)
- 管理契約書(家主不在型で管理業者に委託する場合)
- マンションの場合、管理規約の写し など
これらの書類は、発行から◯ヶ月以内といった期限が設定されているものもあるので、タイミングに注意。申請パターンや自治体によって必要書類は変わるので、役所のHPや問い合わせ窓口で確認しておくと安心です。
申請タイミングと固定費を抑える工夫
物件を借りる場合、契約と同時に家賃が発生するため、申請中は収入がなくても毎月の固定費がかさんでしまうのが難点です。そこで、つぎの3つのポイントを抑えておきましょう。
契約前に相談できることは相談しておく
例えば、用途地域的に旅館業は可能かどうかを事前に調べる。NGなら別物件を探すほうがスピーディーだったり、民泊に切り替えて、180日運用で利益が出るかを収支計算したほうがいいですね。
資料や書類を先に集めておく
消防署への確認や登記簿謄本の取得、オーナーへの承諾取り付けなど、物件契約後だとバタバタしやすいです。早めに下調べ&準備しておきましょう。
オーナーと交渉してみる
場合によっては「許可が下りるまで、家賃を少し猶予してもらえませんか?」などのお願いができるかもしれません。ダメ元でも相談してみる価値はありますよ。
都市部と地方でこんなに違う?
ここでは都市部と地方の違いについて解説します。
都内・大都市の場合
- 独自の条例が追加されているエリアも多く、営業日数や営業時間に制限がかかることがある
- 人口密度が高いので、近隣とのトラブル対策(騒音やゴミ出しなど)も考えておく必要あり
- 物件の家賃や初期費用も高めなので、収益計算はしっかりと
地方や観光地の場合
- 旅館業法を使って「民宿や簡易宿所の許可を取りやすい」自治体もある
- 過疎化や地方創生の文脈で民泊を歓迎している地域も少なくない
- ただし、古民家などの改修が必要な場合は追加コストがかさむことも
- 観光地だと宿泊需要はあるが、大手ホテルや旅館との競合も激しい場合もある
一見、都内のほうが稼働率を期待できそうですが、独自規制などで思ったほど営業できないケースも。一方で、地方では物件コストや規制のゆるさで有利になるかもしれません。結局は「自分がやりたい物件とエリア」でどんなルールがあるかを早めに確認するのが大事ということです。
実際に弊社が苦労した話 〜立ち上げ時のリアル〜
ここからは、弊社が自社物件を立ち上げるときにぶつかった壁や、そこから学んだコツをご紹介します。
どこの部署に何を相談すればいいのかわからない
旅館業法なのか、住宅宿泊事業法なのか、そもそも用途地域は何に該当するのか……最初はとにかく手探りでした。建築指導課に行くべきか、保健所に行くべきか、消防署が先か……。試行錯誤の末、物件所在地の自治体に電話して「こういう形で民泊を始めたいんですけど、まずどこに行けばいいですかね?」とざっくり質問してみたら、担当部署を丁寧に教えてもらえました。「まずは市の観光課で概要を確認→保健所で旅館業の事前相談→建築指導課で建築基準法チェック」という流れがわかり、無駄足を減らせました。
一つの地域に集中して物件を増やすと楽
最初は「いろんなエリアに分散して物件を持とうか?」と考えていましたが、結果的に同じ地域で同じような物件を複数展開するほうが圧倒的に効率が良いと実感しました。理由は、許可に必要な書類や消防設備の基準がほぼ同じになるためです。自治体ごとにルールがガラッと違うと、また1から学び直し・交渉し直しになります。
同じ地域で続けて申請していると、役所の担当者さんも「あ、この前も申請に来ましたよね?」となって話が通りやすくなり、申請のハードルが段々下がっていきました。
経験者とのつながりが最大の近道
役所の窓口だけではわからない“リアルな話”がたくさんあります。たとえば「ここって実は住民感情が厳しいから説明会ちゃんとやったほうがいいよ」とか、「あそこの消防署は消火器の配置に独特のルールがあるから注意してね」みたいな細かい情報です。すでに民泊を始めている人と知り合えると、こういった実用的なアドバイスを先に仕入れられて、余計な出費を抑えられました。
「ネットで調べても情報がバラバラでよくわからない!」という方は、ぜひ経験者とつながる工夫をしてみるといいですよ。もちろん弊社でもサポートいたしますので、気になる方はお気軽にご連絡ください。
まとめ
民泊を始めるには、まず「どの法律で行うか」を選択しなければなりません。住宅宿泊事業法、旅館業法(簡易宿所)、特区民泊と、それぞれ特徴が異なるので、自分がやりたいスタイル・やりたいエリアに合った制度を選びましょう。さらに、許可や届出には様々な書類や設備基準があるので、準備する順番やタイミングを意識すると、余計な家賃や改修費用を抑えられます。
• 都市部は需要が大きい反面、条例による規制や近隣住民とのトラブル予防が大変かもしれません。
• 地方・観光地は許可が通りやすい場合がある一方、古民家など改装費用や集客方法に工夫が必要なことも。
いずれにせよ、最終的に頼りになるのは「すでに同じ地域で民泊を始めている人」の生の声です。調べるよりも先に、経験者に話を聞くことで、わからない部分を一気にクリアにできることも多いです。
今後のコミュニティオープン予定&講座・管理相談のご案内
弊社では今後、民泊オーナー同士が情報交換できるコミュニティをオープンする予定です。まだ具体的なスケジュールはお伝えできませんが、オープンの際は改めてお知らせいたしますので、楽しみにお待ちください。
また、以下のサービスも行っています。興味のある方はお気軽にアクセスしてみてください。
住宅宿泊管理業登録実務講習=民泊管理運営に関する講座へのお申し込み
• 民泊カレッジ
→ 初めての方でも安心して学べるオンライン講座です。住宅宿泊事業法、旅館業法などの手続きの流れもわかりやすく解説しています。
民泊物件の管理相談
• GRADIA
→ 申請手続きのサポートや、物件管理のアウトソーシングなど幅広くお手伝い可能です。「とりあえず相談してみたい」という段階でも大歓迎です。
一緒に民泊の魅力を楽しみながら、あなたらしい宿泊運営を実現していきましょう!