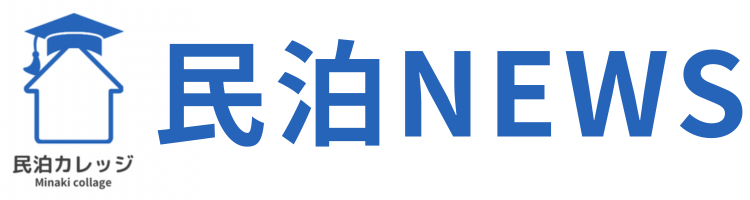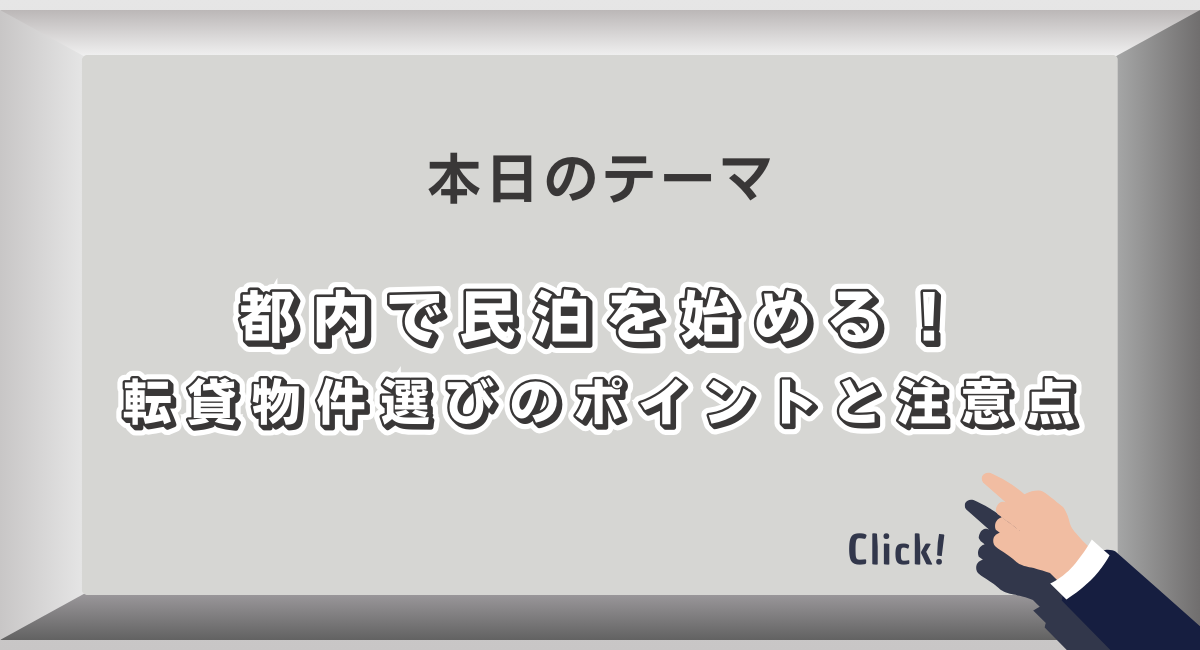東京や大阪、地方都市で民泊(住宅宿泊事業)を始める際には、自分で物件を所有せず賃貸物件を転貸(サブリース)して運営するケースが多くあります。しかし、通常の賃貸契約とは異なる注意点が数多く存在し、初心者が知らずに契約してしまうと思わぬ失敗や損失につながることも…。本記事では、都内で民泊を始めるための転貸物件選びについて、初期費用が高くなる理由から契約時の注意点、悪質な仲介業者の見極め方、さらに実際の失敗事例と回避策、活用すべき情報源やネットワークまで、具体例や実践的アドバイスを交えて解説します。初心者の方でも失敗しない物件選びができるよう、ポイントを押さえていきましょう。
初期費用が高くなる理由
民泊可能な転貸物件を借りる際の初期費用は、一般的な賃貸物件に比べて高額になりがちです。主な理由として以下が挙げられます。
- 民泊可能物件が非常に少ないため:都内で「民泊可」の物件は供給が少なく希少です。需要に対して供給が追いついておらず、物件情報サイトに掲載された瞬間に借り手がついてしまうほど取り合いになっている状況です 。弊社の感覚だと2024年に入った段階で、検索で引っかかる大手賃貸サイトや不動産情報から民泊物件を探し出すのはほぼできなくなったと感じ始めました。10件の不動産仲介会社に電話して一件くらい「探してみます」と言ってもらえればいい方で、今は民泊といった時点で電話先の冷遇・・・その結果、競争が激化し家賃相場が割高になる傾向があります。オーナー(貸主)側も「民泊に使いたい」という借り手が多いことを知っているため、通常より高い賃料や条件を設定しがちです。
- オーナーや管理会社による賃料・保証金の上乗せ:民泊用途で貸す場合、オーナーがリスクや手間を考慮して礼金(保証金)を多めに要求したり、賃料自体を高めに設定するケースがあります。例えば通常なら礼金1~2ヶ月のところを、民泊運用なら敷金3ヶ月以上求められる、といったことも珍しくありません。これは、短期宿泊で不特定多数が出入りすることで起こり得る設備消耗や近隣トラブルへの備えとして、貸主がリスクヘッジしている面があります。
- 仲介業者の手数料や紹介料が割高:民泊可能物件を専門に扱う不動産仲介業者も存在しますが、そうした業者の中には通常より高額な手数料や初期費用を設定しているところもあります。実際、民泊ブームに伴い「物件を紹介してくれる業者さんの一部は強気な初期費用の設定になっている」との報告もあります 。具体的には、通常は借主が支払う仲介手数料は家賃1ヶ月分程度が上限ですが、民泊物件ではそれ以上のコンサル料や物件紹介料が上乗せされる場合があります。
- 消防設備工事など法令順守のコスト:賃貸物件を民泊用途に転用するには、法律上求められる設備を整える必要があります。例えば自動火災報知機、誘導灯、消火器、スプリンクラーなどの消防設備は義務付けられており 、物件によってはそれらを新設しなければなりません。その費用は数百万円規模になることもあり、初期費用を大きく押し上げる要因です 。実際に「物件自体は民泊可能だが、“特定一階段等防火対象物”に該当し消防設備に莫大な費用がかかるため断念した」というケースもあります 。このように法令順守コストが予想以上に掛かる物件も存在します。
- その他初期投資:物件取得費用以外にも、民泊運営には家具・家電の購入費用や内装工事費用、民泊届出の申請費用などが必要です。特に家具家電や内装にこだわると数十万円単位の出費になります。物件によっては現状のまま利用できずリフォームが必要な場合もあり、その分の費用負担も考慮しなければなりません。これら運営準備のコストも合わせると、開業までのトータル初期費用はさらに高額になります。
▶対策アドバイス: 初期費用を抑えるためには、まず信頼できる業者に費用内訳を詳細に確認しましょう。仲介手数料や敷金・礼金の交渉も可能です。実際、「かなり高めの初期費用を提示されたが交渉の末に大幅に値下げしてもらい、数ヶ月分のフリーレント(賃料無料期間)まで付けてもらえた」という成功例もあります 。交渉のコツは単に「安くしてほしい」というだけでなく、こちらも長期で借りる意思や誠実な運営計画を示し、双方にメリットがある提案をすることです。また、物件探しの段階で消防署等への事前相談を行い、想定される設備設置コストを把握してから契約判断することも大切です 。必要に応じて物件オーナーと費用負担について交渉し、一部費用をオーナー側で負担してもらうことができないか打診してみるのも有効でしょう。
悪質な仲介業者と良心的な業者の見極め方
民泊可能物件を探す際には、不動産仲介業者の協力が不可欠です。しかし中には悪質な業者も存在するため、見極めが重要になります。悪質な仲介業者に引っかかると、不当な費用を支払わされたり、契約トラブルに巻き込まれる危険があります。一方、良心的な業者は初心者の強い味方となってくれます。以下に悪質業者の特徴と良心的な業者の特徴を比較表にまとめました。
| 悪質な仲介業者の特徴 🟥 | 良心的な仲介業者の特徴 🟩 |
|---|---|
| 手数料や独自の費用が不透明:法定の仲介手数料以上の高額な紹介料等を要求す 高額な「コンサル料」「○○サポート料」など名目が不明瞭。 | 手数料が適正:仲介手数料は家賃1ヶ月分程度など法規範内で明確。費用内訳を丁寧に説明してくれる。 |
| 契約内容が曖昧:民泊可能かどうかの重要事項を口頭で済ませ書面に残さない。物件の制限事項(用途地域による営業日数制限や消防法令適合状況など)を十分に把握せずに「大丈夫」と安易に勧めてくる。 | 情報開示が徹底:民泊の許可条件や物件の制約を事前に調査し、契約前にすべて説明してくれる。オーナーの承諾書や管理規約の確認など必要書類の取得にも協力的。 |
| 対応が強引:内見や契約を急かし、「今決めないと他に借りられる」などプレッシャーをかけて冷静な判断をさせない。質問に対して明確に答えずはぐらかす傾向。 | 対応が誠実で丁寧:契約者の不安や疑問に真摯に答えてくれる。契約を急がせず、十分に検討する時間を与えてくれる。必要に応じて行政手続きや法律面の相談にも乗ってくれる。 |
| 評判が悪い:ネット上の口コミや他の民泊運営者から「高額なだけでサポートがない」「トラブルが多い」等の評判が聞こえる。 | 実績と信頼:民泊物件紹介の実績が豊富で、利用者からの評判も良い。SNSやコミュニティで名前が挙がる業者でも、評判が安定して良好。 |
▶見極めアドバイス: 業者選びで失敗しないためには、契約前にその業者の評判をリサーチすることが効果的です。業者名でネット検索し「口コミ」「評判」をチェックしたり、民泊運営者が集まるSNSコミュニティで「○○という会社で契約を検討しているがどうか?」と質問してみると良いでしょう。実際、Twitter(現X)上や民泊関連のオンラインサロンでは「民泊やレンタルスペース向け物件を紹介してくれる不動産業者」の情報が飛び交ってい て、そこで名前が挙がる会社はそれなりにこの業界で知られた存在なので、過去の取引事例などを調べられます。ただしSNSで人気だからといって必ずしも安心ではないため、最終的には契約内容を自分で確認する姿勢が大切です。契約条件や費用について不明点があれば書面での説明を求め、曖昧な回答しかしない業者とは契約しないほうが無難です。また、「民泊物件あります」などと違法に無免許で紹介してくるようなブローカーには絶対に関わらないようにしましょう(不動産仲介は宅地建物取引業の免許保持者しかできません)。信頼できる業者は、こちらが慎重に確認する姿勢を見せても敬遠せず、むしろ協力してくれるものです。
契約時に注意すべきポイント
物件が見つかり契約段階に進む際には、通常の賃貸契約以上に慎重な確認が必要です。民泊転貸特有の契約上のリスクに備えるため、以下のポイントに注意しましょう。
1. 契約形態の確認:定期借家契約か普通借家契約か
契約が定期借家契約(定借)になっていないか必ず確認してください。定期借家契約とは契約期間が満了すると更新がなく終了する契約です。例えば「1年の定期借家」の場合、1年後に貸主の判断で契約を終了でき、借主は退去を求められる可能性があり ます(定期借家契約はデメリットだらけ?オススメ出来ない理由3選 | ルームキューブ台東区賃貸管理センター)。貸主と再契約の合意ができれば延長できますが、法律上正当な理由がなくても貸主は契約を終了可能なので民泊運営では初期投資回収に時間がかかるため、1~2年で契約終了となっては採算が取れないリスクが高いです。特に悪質なケースでは「契約時は定借と告げられず、更新できるものと思っていたら実は更新なしで退去せざるを得なかった」というトラブルも起こりえます。
★対策: 可能な限り普通借家契約(更新が可能な契約)で契約することをおすすめします。どうしても定期借家契約しか選択肢がない場合は、再契約の見込みについて貸主側と事前によく話し合いましょう。「契約満了後も貸してもらえる可能性はあるのか」「契約延長の場合の条件はどうなるか」を確認し、できれば書面や覚書で合意を残すと安心です。また、定借で契約する場合は初期費用(敷金や内装費等)の減額交渉を強めに行うなど、短期間で撤収になってもダメージを最小化できるよう準備しておきましょう。
2. 契約書・特約事項の細部確認
契約書に記載された内容は隅々まで確認しましょう。特に特約事項(通常の契約条項に追加・変更して定める事項)は小さな文字で書かれていて見落としがちですが、非常に重要です。例えば以下のような点です。
- 原状回復義務・退去時清算:退去時のルームクリーニング費用や原状回復費用の負担について特約で定められていることがあります。契約前にクリーニング費用の額や負担区分を確認しまし (住宅:賃貸住宅の入居・退去に係る留意点 – 国土交通省)0】。不明な点は遠慮せず業者や貸主に質問し、納得するまで説明を受けてください。例えば「退去時にクリーニング費用○万円を借主負担とする」等の特約があれば、その金額を事前に考慮して収支計画に入れる必要があります。
- 鍵交換費用・設備費用負担:入居時や退去時の鍵交換費、家具家電の撤去費などが特約に盛り込まれている場合もあり (住宅:賃貸住宅の入居・退去に係る留意点 – 国土交通省)0】。鍵交換費用は借主負担が一般的ですが、相場を超える高額な設定になっていないか注意します。
- 中途解約違約金:契約期間内に借主都合で解約する場合の違約金条項も確認しましょう。例えば「1年未満で解約した場合は家賃1ヶ月分の違約金」などの規定です。民泊運営は状況の変化(法律の変更や収益悪化など)で途中撤退せざるを得ない可能性もあるため、この違約金があまりに高額だと撤退コストが大きくなります。違約金条項がある場合はせめて妥当な水準か検討し、不当に高ければ交渉や契約見送りも視野に。
- その他特約:民泊用途特有の取り決めもあり得ます。例えば「近隣から苦情が一定数あった場合には即時解約できる」等の条項や、「宿泊者の迷惑行為による損害は全て借主負担とする」等です。こうした条項があると想定外の費用負担や急な営業停止につながる可能性がありますので、内容とリスクをよく吟味しましょう。必要に応じて削除や修正を交渉することも大切です。
★対策: 特約事項は難解な文言も多いので、不安であれば専門家に確認してもらうのも一案です。契約前に時間をもらい、宅地建物取引士の友人や、民泊に詳しい行政書士・弁護士などに相談できればベストです。また国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」なども参考になります。 (住宅:賃貸住宅の入居・退去に係る留意点 – 国土交通省)契約書に判を押す前に、自分が納得できない条件は残さないことが鉄則です。
3. 民泊運営の許可条件を満たしているか
賃貸物件で民泊を営むには、貸主(オーナー)の承諾が必要なのはもちろん、マンション物件であれば管理規約上民泊が許可されていることが不可欠 です。契約時に以下を確認しましょう。
- オーナーの承諾書:住宅宿泊事業の届出の際に「賃貸人の承諾書」が必要 です。口頭で「いいよ」と言われただけでは不十分なので、必ず書面で承諾をもらうようにします。契約書の特約に「本物件で住宅宿泊事業を営むことを貸主は許可する」旨を入れてもらう方法もあります。
- 管理組合の承認:マンションの場合、建物の管理組合が民泊を禁止していないか確認が必要です。管理規約で民泊(宿泊施設としての利用)を禁止している場合、オーナーの承諾があっても法的には民泊営業できません。行政への届出時にも「マンション管理組合の承諾書類」の提出が求められ ます。契約前にオーナーから管理組合に話を通してもらい、承諾書を用意できることを確認してください。
- 用途地域の制限:物件の所在地が住宅専用地域などの場合、自治体の条例で営業日数や営業可能曜日に制限があることがあります。例えば地域によっては「平日不可、週末のみ民泊可」といったルールがあるケースも報告されてい ます。契約前に物件所在地の自治体窓口や条例を調べ、年間何日・どの曜日に営業可能かを把握しましょう。
- 物件の構造・防火規制:前述のとおり物件の構造によっては追加の消防設備設置義務が発生します。特に木造3階建以上や**避難経路が一つしかない建物(特定一階段等防火対象物)**は規制が厳しく、事実上営業困難なケースもあります。契約前に消防署へ物件図面を持ち込んで相談する、または仲介業者に物件の防火対象区分を確認してもらいましょう。
★対策: 上記の許可条件については契約前チェックリストを作って一つ一つ潰していくことが重要です。「オーナー承諾書取得」「管理規約確認」「用途地域確認」「消防署相談」など、やるべきことを明確にして抜け漏れを防ぎましょう。もし一つでも不明点が残る物件は契約しない勇気も必要です。「契約してから考えよう」は民泊では通用しません。許可が下りず営業できなければ毎月の家賃が丸損になります。リスク要因は事前に取り除いてから契約締結するようにしてください。
実際の失敗事例とその回避方法
最後に、実際に民泊用に転貸物件を借りて失敗してしまった事例と、その教訓から学ぶ回避策を紹介します。
失敗事例1:年間180日営業制限で収支がゼロに…
ケース:民泊新法のもとで届出を行い、都内の賃貸マンションで民泊を始めたAさん。物件の立地はまずまずで、稼働率も平均程度は確保できていました。しかし住宅宿泊事業法の規定により年間営業日数は180日までに制限されています。結果、どんなに頑張っても年間の半分しか部屋を稼働できず、売上は想定の半分程度にとどまりました。それにも関わらず家賃や光熱費、ローンなどの固定費は年間通じて発生するため、1年運営してみたら利益がほとんど残らず収支トントンという状況に…。場合によっては赤字すれすれだったそうです。
原因分析:この失敗の原因は収支計画の見積もり甘さと、180日ルールの影響を軽視したことにあります。2018年施行の民泊新法によって年間営業日数が180日に制限されたため、限られた日数で高い稼働率と宿泊単価を達成しなければ十分な利益が出しにくい状況 になりました。特に賃貸物件で家賃を支払いながら運営する場合、自宅運用より利益を出すのが格段に難しくなります。ある分析によれば、自前物件で民泊運営しても諸経費差し引き月5万円利益が出れば良い方で、賃貸物件だと利益を生み出すことすら難しいとされてい ます(民泊新法が不動産投資に与える影響とは? | HowMaマガジン|家を売る、いつか売るに備えるWEBメディアです)。Aさんもこの壁にぶつかった形です。
回避策:180日ルール下で利益を出すには、入念な収支シミュレーションが欠かせません。契約前に想定家賃・運営コスト・稼働率から年間収支を計算し、180日運用でも黒字が確保できるか確認しましょう。例えば「平均宿泊単価×想定稼働日数-(家賃+光熱費+清掃費+手数料)」を算出し、利益が出るラインの稼働率を把握します。その稼働率が現実的かどうか、同エリアの競合物件の状況や観光需要も調査しましょう。どうしても180日では利益が出にくい場合、以下のような対策も検討できます。
- 特区民泊や旅館業の許可取得:東京23区内でも大田区など国家戦略特区に指定された地域では、条件を満たせば180日制限なく営業できます。また簡易宿所など旅館業法の許可を取得すれば年間を通じて営業可能です。ハードルは上がりますが、本格的に利益を出したいなら視野に入れても良いでしょう。
- ミックス運用:180日制限の範囲内で民泊運用し、残りの日はマンスリー貸し(1ヶ月以上の賃貸)や長期ウィークリー貸しで埋める手法 (民泊とマンスリー併用型で売上を最大化!法律違反にならない方法 …) (【超危険!】民泊物件を定借で借りると負け確です。 – YouTube)。1ヶ月以上の賃貸であれば旅館業法に抵触せず合法的に運用でき ます。繁忙期は短期民泊、閑散期は中長期賃貸と使い分けることで空室損失を減らし、収益の底上げを図ることが可能です。
- 物件規模の見直し:利益が出にくい場合、無理に高家賃の大型物件を借りるより、家賃の安い小型物件や郊外物件で堅実に運営する方がよいケースもあります。特に初めての民泊運営であれば、背伸びしすぎず小さく始めて様子を見ることで、大失敗を避けやすくなります。
失敗事例2:契約の落とし穴で営業不能に…
ケース:副業で民泊を始めようとしたBさんは、「オーナー許可済み」という触れ込みの都内アパート物件をある仲介業者経由で契約しました。ところがいざ届出を進めようとしたところ、マンションの管理規約で宿泊業禁止が判明し管理組合からストップがかかってしまいました。さらに契約書を見ると貸主の承諾は口頭のみで書面がなく、正式な許可を得られない状態でした。結局その物件では合法的に民泊営業はできず、Bさんは高い初期費用を払った末に泣く泣く解約する羽目に…。しかし定期借家2年契約だったため途中解約の違約金まで発生し、初期費用もほとんど戻らない結果となりました。
原因分析:Bさんの失敗は契約前の確認不足に尽きます。「オーナーOK」という言葉を信じてしまい、管理規約の確認や承諾書の取得を怠ったこと、また契約条件(定期借家や違約金条項)を深く検討しなかったことが要因です。仲介業者も民泊の専門知識が不足していたのか、用途地域の制限や管理規約について十分な説明をしていませんでした。結果的に重要事項が契約書に明記されないまま契約してしまい、後から「できないこと」が判明した形です。このように民泊物件では、「契約できた=運営できる」ではない点に注意が必要です。
回避策:このケースから学べるのは、**「契約前に疑問点はゼロにする」**ことの大切さです。具体的な回避策として:
- 前述のとおり管理規約やオーナー承諾書を事前に確認・取得すること。口頭の約束は無効と心得ましょう。承諾書は行政提出用だけでなく、トラブル時の証拠にもなります。
- 仲介業者任せにせず、自分でも物件の法的条件をリサーチすること。用途地域によっては営業日数が制限される地域があるこ と、建物の防火性能によって必要設備が異なること 、基本的な知識を持っているだけで業者からの提案内容を見極められます。少し勉強しておくだけで「この物件は大丈夫か?」とチェックすべきポイントが見えてきます。
- 契約条件の交渉と文書化:定期借家契約しか選べない場合でも、先述したように再契約の取り決めを事前に交渉し書面に残す、違約金条項を緩和してもらう、などリスク軽減の交渉はできます。交渉内容は口約束ではなく書面(契約書や覚書)に明記してもらいましょう。良心的な貸主であれば、誠意を持って頼めば配慮してくれる可能性があります。
- 撤退プランを用意:最悪、契約後にどうしても運営継続が難しくなった場合の撤退プランも考えておきます。違約金を払ってでも早期解約した方が損失が少ないのか、あるいは180日民泊は諦めてマンスリーマンションとして貸し出すことで契約期間を乗り切るか、など損切りの判断基準を決めておくと、いざという時パニックにならずに済みます。
以上のように、契約前の段取りと万一のプランBまで用意しておくことで、契約の落とし穴による深刻なダメージを回避できます。
民泊運営者が活用すべき情報源やネットワーク
物件選びから契約、運営に至るまで、情報収集と人脈づくりは民泊事業の成功において欠かせません。特に転貸で民泊を始める初心者の方は、孤立せず様々な情報源やネットワークを活用しましょう。
- SNS(X・Twitter、Facebook等)のコミュニティ:民泊運営者や物件紹介業者が集まるコミュニティが多数あります。Twitter上では**「#民泊」「#民泊物件」などのハッシュタグで最新情報を発信しているアカウントも多く、民泊可能物件の募集ツイートが流れてくることもあります。またFacebookの民泊グループやLINEオープンチャットなどで、運営者同士が情報交換している場もあります。ある民泊運営者は「民泊サロンやXにいる物件紹介業者さんの情報に飛びつくのが一番効率が良い」と述べています (〖民泊アレコレ〗副業で民泊を始めたいけど「物件がない!」と思っている方へ(初心者の私より)|ASAMI ICHIBA)。実際、SNS経由で良物件をゲットした例も多々あります。ただし前述のように人気物件情報は競争が激しい**ため、SNSで有益情報を得たら迅速に行動するフットワークも必要です 。
- 民泊関連のオンラインサロン・勉強会:近年、民泊をテーマにしたオンラインサロン(有料コミュニティ)や勉強会・セミナーが増えています。そこでは経験者から直接ノウハウを学べたり、非公開の物件情報を紹介してもらえることもあります。同じ志の仲間ができることで、モチベーション維持にも役立つでしょう。ただしサロンの中には質が玉石混交のものもあるため、選ぶ際は主催者の実績や参加者の口コミを参考にしてください。
- 信頼できる不動産業者ネットワーク:民泊物件に強い不動産会社を見つけたら、その担当者との関係を大切にしましょう。一度うまく契約できれば、次の物件を紹介してもらえたり、運営中に困ったとき相談に乗ってもらえるかもしれません。また、不動産会社同士のネットワークで別エリアの情報を持ってきてくれる場合もあります。最初は小さな物件でも丁寧に運営し実績を作ることで、業者側から見ても「安心して任せられる借主」となり、好条件の物件を優先的に紹介してくれるようになることもあります。
- 民泊管理代行会社や清掃会社からの情報:物件選びとは直接関係ありませんが、民泊の運営代行会社や清掃会社も業界の情報源として有用です。彼らは多数の民泊物件を扱っているため、どのエリアが狙い目か、どういった物件が高稼働かなど生のデータを持っています。打ち合わせの中で雑談的に聞いてみると有益なヒントが得られることがあります。また代行会社によっては「物件紹介サービス」を提供しているところもありますので、契約先候補として検討してみてもよいでしょう。
- 行政機関や業界団体の情報:各自治体の住宅課や保健所は民泊の届出相談に乗ってくれるほか、条例改正など最新の情報を教えてくれます。定期的に自治体のウェブサイトやニュースリリースをチェックしましょう。また、民泊関連の業界団体(民泊協会や地域の民泊連絡会など)が開催するセミナーや講習会に参加するのもおすすめです。法改正情報や補助金制度の紹介、運営者同士の交流など得られるものが多いです。
▶総括アドバイス: 情報源は多岐にわたりますが、肝心なのは自らアンテナを張って積極的に情報収集する姿勢です。成功している民泊運営者は総じてフットワークが軽く、ネットワークを駆使しています。最初は右も左も分からないかもしれませんが、一人で悩まずコミュニティに飛び込んでみましょう。例えばTwitterで気になる民泊ホストをフォローしてみる、関連する勉強会に思い切って参加してみる、といった行動が次のチャンスを呼び込むかもしれません。また、得た情報を鵜呑みにするのではなく必ず裏を取る慎重さも忘れずに。最終的な判断は自分自身で行い、情報を取捨選択していくことで、失敗のリスクを大きく減らすことができるでしょう。
まとめ:失敗しない物件選びのために
東京で民泊を始めるための転貸物件選びについて、重要なポイントを解説してきました。民泊可能物件の希少性ゆえの初期費用高騰や、悪質な仲介業者の存在、契約上の落とし穴など、初心者にとってハードルに感じることも多いかもしれません。しかし事前に十分な知識と準備を持って挑めば、これらのハードルは乗り越えられます。
最後に、失敗しない物件選びのために大切な心構えをまとめます。
- 計画8割・実行2割:物件契約までにリサーチと準備を徹底しましょう。契約後に「想定外」を発覚させないことが成功の鍵です。
- 信頼できるパートナーを持つ:良心的な不動産業者や先輩民泊ホスト、専門家など頼れる人脈を築いておくと、判断に迷ったとき心強い味方になります。
- 契約書はあなたを守る盾:契約内容に納得いかない部分があれば遠慮せず修正を求めましょう。書面で合意されたことだけが頼りです。
- 常に最悪をシミュレーション:楽観シミュレーションだけでなく、稼働率低迷や途中解約の場合の損失も計算し、それに耐えられる範囲で計画を立てましょう。
- 情報収集を怠らない:民泊業界は法規制や市場トレンドが変化しやすい分野です。アンテナを高く張り、最新情報をキャッチアップする習慣をつけましょう。
これらを念頭に置きつつ、ぜひ理想の物件と巡り合い、東京での民泊運営を成功させてください。初めは大変かもしれませんが、適切な物件選びさえできれば、あとは経験を積みながら改善していけます。あなたの民泊ビジネスの一歩を踏み出す助けになれば幸いです。健闘を祈ります!
もちろん弊社で管理委託を承ることも可能です。本当にその物件が収益が出る物件なのか、最初のこの収支計算の部分から伴走させていただきます!
民泊や短期賃貸を始めても、収益がしっかり出なければ意味がありません。また、たとえ収益があっても、ゲストの満足度が低ければ評価の低下やリピート率の減少につながり、オーナー様の手間や負担が増える悪循環に陥ってしまいます。
そこで弊社では、物件が抱える課題を一つひとつ丁寧に解決しながら、より高い価値を生み出す民泊・不動産管理を行っています。もちろん、“すべてお任せで丸投げ”ではなく、オーナー様と笑顔で協力できるパートナーシップを大切にすることで、双方にとってより良い運営体制を築き上げられると考えています。
「どんな小さな課題でも相談でき、安心して任せられる」——そんな管理サービスを目指して、これからも皆さまの物件運用を全力でサポートしてまいります。ぜひ一緒に、より魅力的で収益性の高い物件へと育て上げていきましょう。
さらに詳しい情報や実績は、弊社ホームページ:株式会社グラディア(https://gradia-estate.com/)にてご覧いただけます。ぜひお気軽にお問い合わせください。※サイトリニューアル中につき、4月中旬まではお問い合わせのみ可能です。