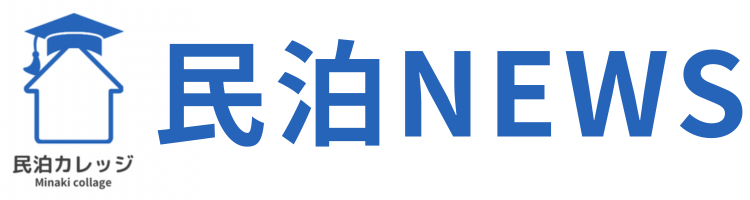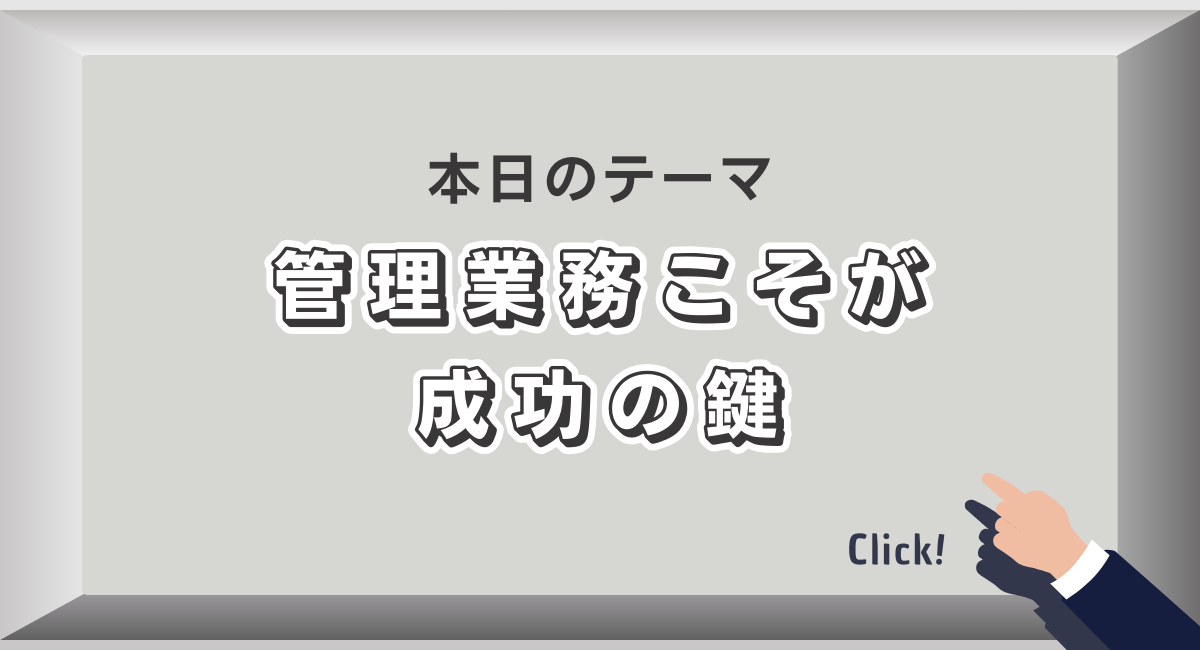こんにちは。今回は民泊(みんぱく)運営における管理の重要性について、私の経験も交えながらお話ししたいと思います。民泊ビジネスに興味を持つオーナーの方々の中には、「物件を用意すればあとは勝手に収益が入るのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、実際の運営現場では管理業務こそが成功の鍵を握っています。この記事では、民泊管理の重要性や、自分で管理する場合と管理会社に委託する場合のメリット・デメリット、日々の管理業務のリアルな実態、そして信頼できる管理会社の選び方について詳しく解説します。
民泊管理が重要な理由
民泊運営において管理が重要である理由はいくつかあります。まず第一に、法律上の必要性です。日本では2018年施行の住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)により、オーナーが物件に居住していない「家主不在型」の民泊では、国土交通省に登録された「住宅宿泊管理業者」へ物件の管理を委託することが義務づけられています 。
適切な管理者を置かないと違法状態となってしまうため、民泊を始める際には管理体制を整えることが前提条件なのです。
第二に、トラブル防止と周辺環境への配慮です。民泊は自宅やマンションの一室を利用するケースも多く、近隣住民とのトラブル(騒音やゴミ出しの問題など)を避けるためにも、しっかりとした管理が欠かせません。管理者が定期的に物件やゲストの様子をチェックし、問題が起きれば迅速に対応することで、地域から信頼される民泊運営が可能になります。
例えば、夜中にゲストが騒いでいるとの苦情が入った場合、誰が対応するのかが明確になっていないと大きなトラブルに発展しかねません。管理者が明確であることは、ゲストに安心感を与えるだけでなく、近隣への安心にもつながります。
さらに、ゲスト満足度と収益性の向上という観点でも管理の重要性は見逃せません。民泊はホテルとは違い、オーナー(または管理者)の裁量でサービス品質が大きく変わります。清潔で快適な部屋を維持し、迅速で丁寧なゲスト対応を行うことは、高いレビュー評価やリピーター獲得につながります。その結果、稼働率が上がり収益も増加するでしょう。近年はコロナ禍からの回復に伴いインバウンド需要も急増しており、2023年春の民泊宿泊数は前年の2倍以上、特に外国人宿泊者数は前年比12.8倍と急増しています (民泊ビジネスの復調顕著 :: 全国賃貸住宅新聞)。
一方で、日本国内の民泊登録物件数は2020年4月の約2.1万件をピークに増加が止まり、2023年3月時点では約1.9万件とむしろ減少傾向にあります。つまり需要は急伸しているのに供給物件は横ばいという状況で、しっかりと管理された魅力的な民泊物件は引く手数多だと言えます。今後のチャンスを活かすためにも、管理の質を高めてゲストに選ばれる物件にすることが重要です。
自主管理と委託管理のメリット・デメリット
民泊の管理方法には大きく分けて**自主管理(オーナー自身で運営管理する)と管理委託(運営代行会社や管理会社に任せる)**の2通りがあります。それぞれに良い点と課題があるため、自身の状況に合わせて最適なスタイルを選ぶことが大切です。ここでは自主管理と委託管理のメリット・デメリットを見てみましょう。
自主管理のメリット
自主管理するメリットは次の3つです。
それぞれ解説します。
コストを抑えられる
管理会社へ支払う手数料が不要のため、収益をそのまま手元に残せます。特に物件数が少ない場合や利益率を重視したい場合、自主管理によって経費負担を減らせるのは大きな魅力です。
自分の裁量で運営できる
ゲストへのメッセージ一つから備品の選定まで、自分の思い通りに管理・サービス提供ができます。ホスト自身のカラーやこだわりを反映したおもてなしを実現でき、ゲストとの直接コミュニケーションを楽しむことも可能です。
現地の状況を把握しやすい
オーナー自ら管理することで、物件やゲストの様子を肌で感じ取れます。小さな不具合にも気づきやすく、改善を迅速に行える点は、自主管理ならではの強みです。
自主管理のデメリット
自主管理するデメリットは次の3つです。
それぞれ解説します。
手間と時間がかかる
約対応から清掃、苦情対応まで全て自分で行うため、想像以上に労力がかかります。ゲストからの問い合わせは深夜でも発生しますし、清掃もチェックアウトの度に必要です。民泊運営では予期せぬトラブルや緊急事態が発生することは珍しくありません 。
例えば深夜に「鍵を失くした」「エアコンが故障した」などの連絡が入ることもあり、24時間体制で臨む覚悟が求められます。
スケールしにくい
自分一人で対応できる範囲には限界があります。物件数が増えたり、本業が忙しくなったりすると、管理が行き届かなくなる恐れがあります。対
応が追いつかずゲスト対応が疎かになれば、評価の低下やトラブル増加につながりかねません。
専門知識が必要
民泊運営には法律の知識(各種届出や条例への対応、宿泊者名簿の管理など)や、多言語でのゲスト対応スキル、適切な価格設定のノウハウなどが求められます。
初心者が手探りで全て行うのはハードルが高く、知識不足によるミスが思わぬ損失やトラブルを招くリスクもあります。
委託管理のメリット
委託管理するメリットは次の4つです。
それぞれ解説します。
運営負担の大幅軽減
なんと言っても自分の時間と手間が大きく省ける点が魅力です。民泊管理会社を利用する最大のメリットは、オーナーが物件運営にかける時間と労力を大幅に削減できることです 。
面倒なゲスト対応や清掃業務から解放されるため、本業に集中したり余暇を確保しながら民泊経営が可能になります。
プロによる高品質なサービス提供
経験豊富な管理のプロが物件を任されることで、ゲストへの対応品質や清掃クオリティが安定します。管理会社は予約受付からチェックイン対応、ゲスト問い合わせ対応、清掃手配、料金設定や予約カレンダー管理までワンストップで代行してくれます。
特に専門業者は多言語対応やトラブル防止のノウハウも持っており、ゲストにとって安心感のあるサービスを提供できます 。
集客力・収益アップ
民泊やインバウンドに特化した運営代行会社であれば、集客面でも強みがあります。例えばAirbnbだけでなくBooking.comや楽天トラベルなど複数の宿泊予約サイトに物件を掲載し、稼働率向上を図ってくれる場合があります 。
また市場動向に応じた動的な料金設定(ダイナミックプライシング)や広告戦略を駆使してくれる会社もあり、自分で運営するより高い収益を期待できるでしょう。
法令遵守・手続き代行
煩雑な行政への届出や報告業務、近隣説明なども委託先がサポートしてくれる場合が多く、運営が初めてのオーナーでも安心です。
住宅宿泊事業者は2ヶ月ごとに宿泊実績を自治体に報告する義務がありますが 、管理会社に委託すればこうした事務作業も任せることができます。
委託管理のデメリット
委託管理するデメリットは次の4つです。
それぞれ解説します。
委託コストがかかる
プロに任せる分、当然ながら費用が発生します。一般的な民泊運営代行サービスの料金は毎月の総売上の15~30%程度が相場です。
さらに清掃費用などが別途かかるケースも多く、利益から差し引かれる形になります。委託料が安すぎる場合はサービス内容を、逆に高額な場合は費用対効果を見極める必要があります(後述するように、費用に見合ったサービスを提供しているかを確認することが重要です 。
運営方針の制約
全てを丸投げすると、自分の思い描くおもてなしが実践しにくくなる場合があります。
例えば、ゲストへの細やかなメッセージを送りたいと思っても、管理会社の標準対応に委ねることになるかもしれません。また物件の設備投資や内装変更などについても、自分だけでは判断できず管理会社と相談が必要になることがあります。
部分委託の難しさ
「清掃だけお願いしたい」「緊急対応だけ頼みたい」といった部分的なサービス利用ができないケースが多いのもデメリットです。多くの管理代行会社はフルパッケージでの契約を前提としており、駆けつけ対応(緊急対応)だけを単独で依頼できるケースは非常に少なく、オプション扱いの場合は割高になる傾向があります。
自分でできる部分は自分で行い、不足部分だけ業者に頼みたいと考えても、条件に合う業者を見つけるのに苦労することもあります。
管理会社選びを誤るリスク
残念ながらすべての業者が高品質とは限りません。もし対応の悪い業者に任せてしまうと、ゲスト対応の遅れや清掃不備などで悪評が立ち、物件の評価が下がる恐れがあります。一度悪いレビューが付いてしまうと挽回に時間がかかるため、委託する際は信頼できる会社を慎重に選ぶ必要があります。
民泊管理業務の実態:現場では何をしているのか
では、実際に民泊の管理者(オーナー自身または委託先の業者)は日々どのような業務を行っているのでしょうか。そのリアルな実態を見てみましょう。
1.予約・問い合わせ対応
ゲストからの予約リクエストや問い合わせメッセージに対応します。予約日程の調整や承認、料金の設定変更など、オンライン上の予約管理システムを駆使して24時間体制で対応することも求められます。特に人気物件では予約が立て込むため、ダブルブッキングを防ぐ管理や、問い合わせに迅速に返答することで機会損失を防ぐ努力が欠かせません。
2.チェックイン・チェックアウト対応
ゲストの到着時・出発時のサポートです。対面で鍵の受け渡しや施設の説明を行う場合もあれば、スマートロックやキーボックスを使ったセルフチェックイン方式を採用する場合もあります。いずれにせよ、ゲストがスムーズに入室・退室できるよう事前案内を徹底し、チェックアウト後は鍵の回収や施錠確認を確実に行います。また、外国人ゲストの場合はパスポート情報の確認・報告といった法定業務も必要です。
3.清掃・リネン交換
ゲスト退室後に部屋を清掃し、次のゲストに備えてリセットします。ベッドメイキングやタオル・リネン類の交換、風呂やトイレの清掃、ゴミの回収・分別、消耗品(シャンプーやティッシュ等)の補充など、多岐にわたります。清潔さは宿泊業の基本であり、口コミにも直結する重要ポイントです。専門の清掃スタッフに委託するケースが多いですが、自主管理の場合はオーナー自身がホテルの客室清掃さながらに丁寧に行う必要があります。
4.設備管理・メンテナンス
エアコンや給湯器、家電製品など備品・設備の不具合がないか常に目を配ります。定期的に動作確認を行い、電球切れや消耗品の故障が見つかれば早めに交換・修理します。特にエアコンや水回りのトラブルは発生しがちで、暑い盛夏にエアコンが故障すると重大なクレームにつながります 。オーナーが常駐していない場合でも、清掃時にスタッフが設備の異常に気づけるようチェックリストを設けておくなど工夫が必要です。万一大きな不具合が起きた際は、迅速に専門業者を手配して対処します。
5.トラブル対応
ゲスト滞在中の緊急連絡や近隣トラブルへの対応も管理者の重要な役割です。よくある事例としては、「深夜にゲストが騒いで近所から苦情」「ゲストが鍵を失くして入室できない」「急にガスや電気が使えなくなった」「設備が故障した」といったものです 。こうした事態に24時間体制で備える必要があり、迅速かつ適切な対処が求められます。私自身、真夜中に物件へ駆けつけて対応した経験もありますが、緊急時にすぐ動ける体制を整えておくことが民泊運営の信頼性につながります。管理会社に委託している場合は、こうした緊急対応も含めて代行してくれるためオーナーは安心ですが、自主管理の場合は家族や知人の協力体制を作っておくなど一人で抱え込まない工夫も必要でしょう。
6.ホスピタリティ提供
これは業務と呼べるか分かりませんが、民泊ならではの付加価値として、ゲストへのきめ細やかな気配りがあります。チェックイン時に近隣のおすすめ観光情報を提供したり、滞在中に困りごとがないかメッセージを送ったり、チェックアウト後にお礼のメッセージを送信したりと、ホテル以上にパーソナルなおもてなしが可能です。こうした対応はレビュー評価で高く評価され、他の競合物件との差別化にもなります。管理会社によっては標準サービスとして地域ガイドを用意したり、マニュアルで一定のフォローアップメッセージを送る仕組みを持っているところもあります。
以上のように、民泊管理の現場ではゲスト対応、清掃、リネン交換、価格設定、予約管理など実に様々な業務をこなす必要があります 。一つひとつは地道な作業ですが、どれもおろそかにできません。私の感覚では、民泊運営は「宿泊業」「清掃業」「不動産管理業」「観光案内業」など複数の顔を持つ仕事だと痛感しています。だからこそ、自分で運営するにせよ外部に委託するにせよ、こうした管理業務の重要性と大変さを理解しておくことが成功への近道になります。実際、物件の維持管理を怠ればゲストからのクレームが増え、リピーターが減少するなど収益にも悪影響が及びます 。裏を返せば、地道な管理業務をしっかりやり遂げることで、ゲストの安全・快適な滞在が守られ、結果的に高評価と安定収益につながるのです。
優良な民泊管理会社を選ぶポイント
自分一人で管理するのが難しい場合、民泊運営代行・管理会社に委託するのは有力な選択肢です。しかし前述の通り、業者選びを誤ると期待した成果が得られない可能性もあります。ここでは信頼できる民泊管理会社を選ぶ際のチェックポイントをまとめます。
それぞれ詳しく解説していきます。
国土交通省への登録
前提として、その会社がきちんと「住宅宿泊管理業者」として国に登録されているか確認しましょう。
無許可の業者に委託することは違法行為につながりますし、信頼性の面でも問題です。
登録業者は2024年3月現在で全国に2,191業者あります (2023年度の住宅宿泊管理業者への全国一斉立ち入り調査の結果 | 事業用不動産Blog | 立和コーポレーション)。契約前に業者の登録番号や許可内容を提示してもらいましょう。
代行費用とサービス内容
提示された費用に見合ったサービスが提供されているかを見極めることが重要です。
月額手数料が安くても対応範囲が限定的では意味がありませんし、逆に高額な手数料ならばそれ相応の高品質なサービスが必要です。料金体系(成果連動なのか固定費なのか、清掃費は含むのか等)を明確に確認し、複数社を比較検討すると良いでしょう。
また、契約前にサービス内容の細部まで説明を受け、納得できるかをチェックしてください。ゲスト対応のレスポンス速度や対応時間帯、オーナーへの報告頻度なども重要なポイントです。
実績や経験
その会社がどの程度の運営実績を持っているかも信頼性の指標になります。
管理物件数や運営年数、取り扱い物件の種類などを確認しましょう。実績が豊富な会社は様々な状況への対応経験があり、トラブル発生時の対処能力も高いと期待できます。
特に自分の物件と同じ地域・同じ規模の物件を扱った経験があるかどうかは重要です。地域特有の条例や慣習、季節変動などを熟知している業者であれば、よりきめ細やかな運営が可能となります。
多言語対応能力
日本人ゲストだけでなく海外からの宿泊客も増えている中、外国語対応が可能かどうかは欠かせないポイントです。
民泊事業では外国人観光客の受け入れは避けて通れない課題であり、したがって管理会社を選ぶ際もスタッフが英語などでコミュニケーション対応できるかを確認すべきです。
例えば問い合わせや緊急電話に英語で対応できるか、ハウスマニュアルを多言語で用意してくれるか、といった点です。言葉が通じないとそれだけでゲストの不安につながりますので、この点に強みを持つ会社は安心です。
緊急対応の体制
深夜や早朝のトラブルにも24時間365日対応してくれるかどうかも重要です。
鍵トラブルや設備故障はいつ起こるかわかりません。コールセンターでの電話対応だけでなく、必要に応じて現地にスタッフが駆けつける体制があるか(いわゆる「駆けつけサービス」)、提携する緊急対応会社があるか、といった点も確認しましょう。
特にオーナーが遠方在住の場合、この体制がしっかりしている会社でないと不安が残ります。大手の管理代行サービスでは24時間対応を掲げているところも多いです。
コミュニケーションと信頼性
担当者との相性や説明のわかりやすさなど、コミュニケーションの取りやすさも重要なポイントです 。契約前の相談時の対応がスムーズか、こちらの質問に丁寧に答えてくれるかなどをチェックしましょう。
長く付き合うパートナーとなるので、信頼関係を築ける会社かどうか直感も含めて見極めてください。
以上のポイントを踏まえて管理会社を選べば、大きな失敗は避けられるはずです。ぜひ複数の業者から話を聞いて比較し、納得のいく委託先を見つけてください。
まとめ
民泊運営において、管理は地味ながら最も重要な要素です。私自身、管理業務の現場を経験する中で「管理がしっかりしていれば民泊事業の9割は成功すると言っても過言ではない」と感じています。この記事で述べたように、法令遵守やトラブル防止、ゲスト満足度向上など、管理には多方面への気配りと専門知識が求められます。
自主管理と委託管理のどちらを選ぶかは、オーナーそれぞれの事情によって最適解が異なります。時間的・地理的に余裕があり、自らホスピタリティを提供したい方は自主管理にやり甲斐を見いだせるでしょう。一方で、本業が忙しかったり遠方に物件をお持ちだったりする方、あるいは運営のプロに任せて効率的に収益を上げたい方は管理会社への委託が有力な選択肢となります。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分に合った運営スタイルを選んでいただければと思います。
大切なのは、どんな形であれ民泊の管理をおろそかにしないことです。ゲストの満足と安全を第一に考え、物件を適切に維持管理することで、民泊事業は初めて軌道に乗ります。「民泊管理のリアル」を知った皆さんが、自信を持って民泊運営に取り組めることを願っています。困ったときはプロの力を借りるのも一つの手ですので、悩んだ際にはぜひ相談してみてくださいね。
もし、「もう少し専門的な内容を学びたい」「住宅宿泊管理業の登録方法を詳しく知りたい」「実際に管理業を始めるための実務講習を受けたい」という方は、ぜひ民泊カレッジの講座を活用してみてください。初心者の方でも分かりやすいカリキュラムで、法規制の最新情報から物件運営ノウハウまで、幅広くサポートいたします。
▼ 講座のお申し込みはこちら [https://gradia-estate.com/lp/]
▼ 民泊管理に関するご相談はこちら [https://gradia-estate.com/]
最新の法規制情報やインバウンド市場の動向を押さえておくことは、民泊ビジネスで成功するための第一歩です。これからも民泊カレッジのブログでは、皆さまにとって役立つニュースや活用術を発信していきますので、ぜひチェックしてくださいね。最後までお読みいただき、ありがとうございました!